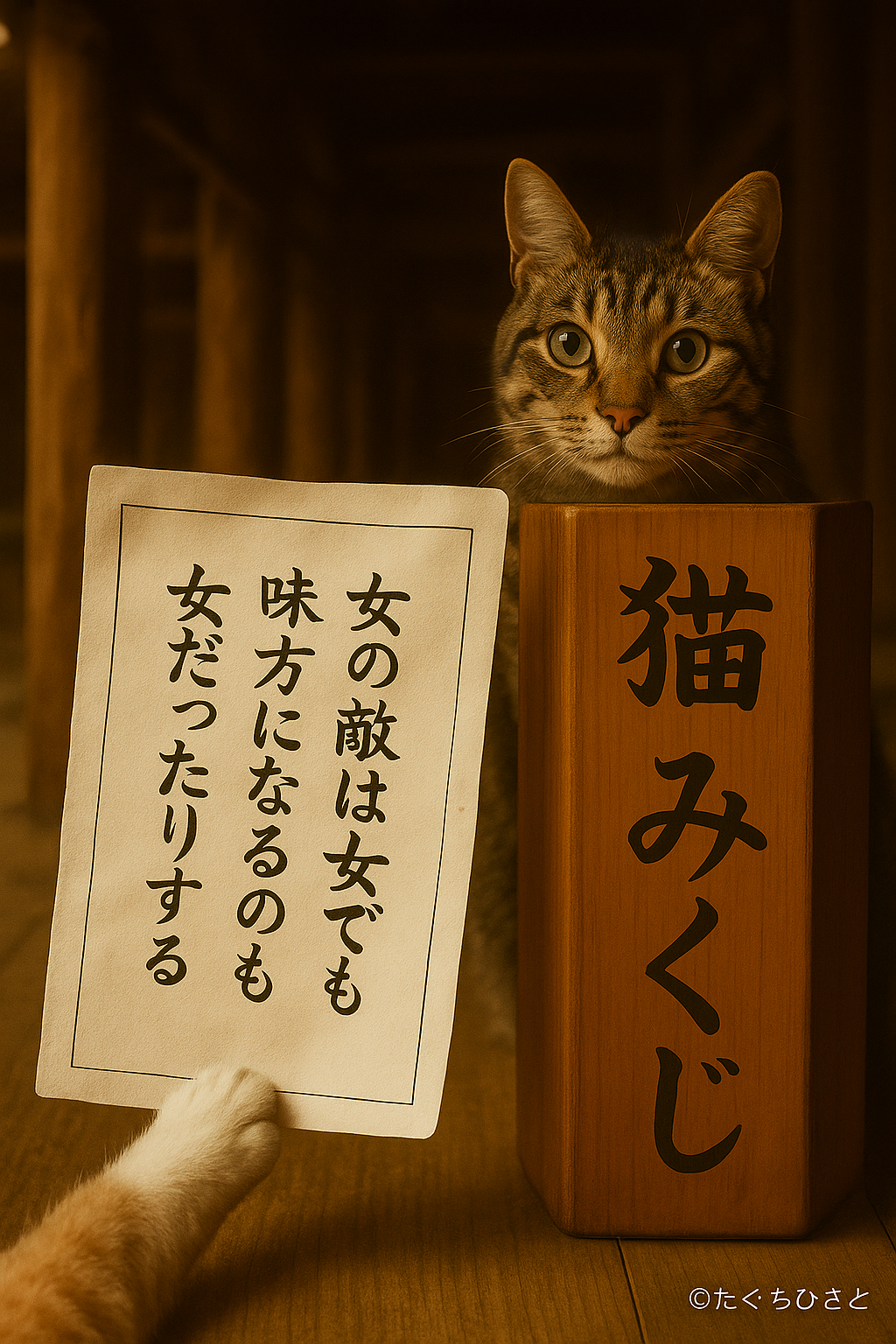🌸「女の敵は女」なんて、本当だろうか?
「女の敵は女」って、よく聞く。だけど、それって本当に真実?
この言葉は、あまりにも有名だ。
まるで格言のように語られ、疑う余地もないように広まっている。
けれど、その言葉の奥にあるものを、改めて見つめ直すときが来ている。
本当に“女の敵”は“女”なのだろうか?
💬「女って怖いよね」そんな会話が当たり前になっていた
学校や職場、ママ友のコミュニティなど、
女性同士の関係には、独特の緊張感があると語られることが多い。
・裏で悪口を言われた
・仲間外れにされた
・マウントを取られた
そうしたエピソードは枚挙にいとまがない。
実際にそういった経験をしてきた人にとって、
「女の敵は女」という言葉は、ある意味で現実を表しているのかもしれない。
しかしその一方で、心から救われた瞬間に寄り添っていたのも、また女性であるという事実がある。
🤝涙に気づき、寄り添う手を差し伸べるのも女性だった
人が本当に辛いとき。
言葉にならない苦しみに押し潰されそうなとき。
その“気配”に敏感に気づき、そっと隣に座ってくれる人がいる。
その多くが、女性だ。
・ただ黙って隣にいてくれる
・何も聞かず、飲み物を差し出してくれる
・泣き顔を見て、抱きしめてくれる
こうした振る舞いに、“共感力”という女性ならではの力がある。
それは訓練されたスキルではない。
社会の中で、日々さまざまな立場を生き抜いてきた中で、
自然と身についた感受性のようなものだ。
🧭なぜ「敵」と思わせるのか――構造としての背景
では、なぜ「女の敵は女」という言葉がこれほど浸透してしまったのか。
そこには、女性が置かれてきた社会的な構造がある。
たとえば、限られたポジションをめぐる競争。
たとえば、容姿や年齢への厳しい評価の視線。
たとえば、「いい母親」「できる女」という理想像への圧力。
こうした背景が、女性同士を“敵”に仕立てあげてしまう土壌を生んできた。
けれど、根本的に争いたいと思っているわけではない。
むしろ、多くの人は「理解されたい」「認められたい」と願っているだけ。
その願いがすれ違うとき、
「競争」や「嫉妬」として現れるのだ。
🌷“味方”になる力を、女性は本来持っている
一方で、女性同士だからこそ持てる共感や、
体験に基づく理解もまた、強い。
・生理や妊娠、更年期といった身体の変化
・家庭と仕事の両立に悩む日々
・社会からの偏見や期待との葛藤
そうした課題を、当事者として共有できる存在は限られている。
だからこそ、女性同士が支え合えたときの安心感は、言葉にできないほど深い。
そして、そうした支え合いのエピソードも、
実際には多くの場面で存在しているのだ。
📚「敵」よりも、「連帯」の物語を語ろう
物語の語られ方は、社会の価値観を映す鏡である。
これまで、「女の敵は女」と語られてきた背景には、
女性同士の“連帯”の可能性を見えづらくしてしまう構造があった。
でも、これからは違う。
・女性同士がビジネスの場で手を取り合い、プロジェクトを成功に導いた
・子育て中のママたちが互いに支え合い、心の余裕を取り戻した
・見ず知らずのSNS上の投稿に、女性たちが励ましの言葉をかけた
そうした連帯の物語こそ、もっと語られるべきだ。
🪞「敵」という言葉に惑わされずに、関係を見つめ直す
言葉には、現実を形作る力がある。
だからこそ、「女の敵は女」という言葉に、無意識のバイアスが含まれていることを忘れてはならない。
すべての女性が味方であるわけではない。
もちろん、相性の合わない人もいるし、傷つけられることもある。
でもそれは、男性同士でも、男女間でも同じこと。
「女性だから」という理由だけで敵視するのは、
本質を見誤ってしまう行為ではないだろうか。
💡本当の“敵”は、孤独と分断
人を最も苦しめるのは、分断された状態での孤独だ。
・「どうせ女同士はうまくいかない」と決めつけること
・「助けて」と言えない空気をつくってしまうこと
・「理解されない」と思い込んでしまうこと
こうした感情が積み重なると、関係性の扉は閉じてしまう。
だからこそ、「連帯」の可能性にもう一度目を向けたい。
🌼まとめ:「女の敵は女」ではない。「味方にもなれる存在」だ
女性同士の関係は、たしかに複雑で、ときに難しい。
けれど、その中には、圧倒的な優しさと力強さがある。
・寄り添う力
・気づく力
・支え合う力
そうした“味方になる力”は、すでに女性の中にある。
だからこそ、言葉に流されずに、関係性の本質を見つめ直す必要がある。
「女の敵は女」ではない。
本当は――**「女は女の味方になれる」**のだ。
最後に。
今この瞬間にも、どこかで誰かが誰かを支えている。
その姿が、私たちのこれからの社会の希望になる。
この文章が、そうした連帯を思い出すきっかけになれば、幸いです。